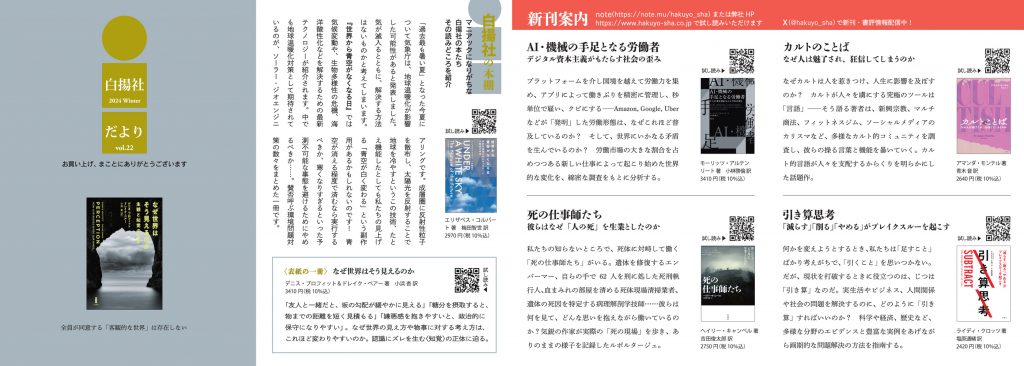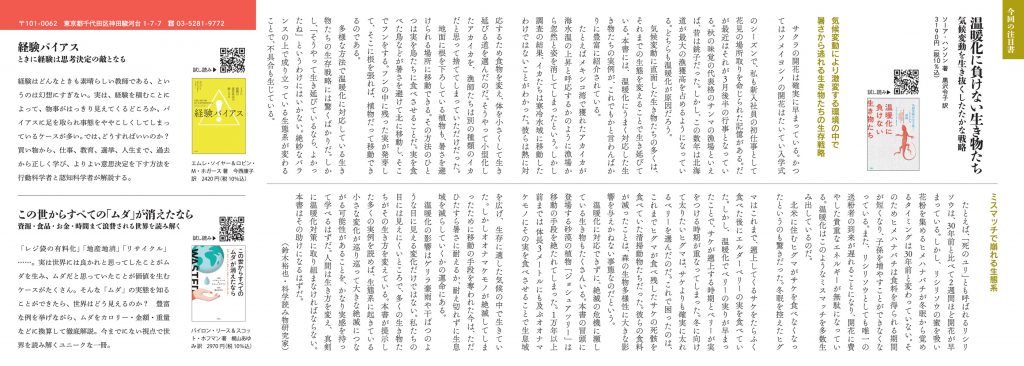科学読み物研究家・鈴木裕也の書評で読む『温暖化に負けない生き物たち』
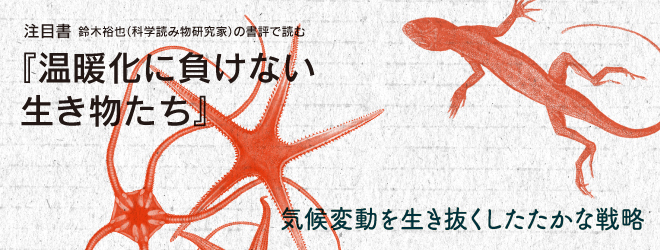
一般向けポピュラーサイエンス読み物を読み漁り、書評を書くライター・鈴木裕也さんが選んだ、イチオシの本を紹介するコーナーです
(白揚社の書籍に挟んでいる「白揚社だよりvol.22」からの転載)
◆
気候変動により激変する環境の中で
暑さから逃れる生き物たちの生存戦略
サクラの開花は確実に早まっている。かつてはソメイヨシノの開花はたいてい入学式のシーズンで、私も新入社員の初仕事として花見の場所取りを命じられた記憶がある。だが最近はそれが3月後半の行事となっている。秋の味覚の代表格のサンマの漁場といえば、昔は銚子だった。しかし、この数年は北海道が最大の漁獲高を占めるようになっている。どちらも温暖化が原因だろう。
気候変動に直面した生き物たちの多くは、それまでの生態を変えることで生き延びている。本書には、温暖化にうまく対応した生き物たちの実例が、これでもかと言わんばかりに豊富に紹介されている。
たとえばメキシコ湾で獲れたアカイカが海水温の上昇と呼応するかのように漁場から忽然と姿を消してしまったという。しかし調査の結果、イカたちは寒冷水域に移動したわけではないことがわかった。彼らは熱に対応するため食物を変え、体を小さくして生き延びる道を選んだのだ。そうやって小型化したアカイカを、漁師たちは別の種類のイカ だと思って捨ててしまっていただけだった。
地面に根を下ろしている植物も、暑さを避けられる場所に移動できる。その方法のひとつは実を鳥たちに食べさせることだ。実を食べた鳥などが暑さを避けて北に移動し、そこでフンをする。フンの中に残った実が発芽して、そこに根を張れば、植物だって移動できるのである。
多様な方法で温暖化に対応している生き物たちの生存戦略には驚くばかりだ。しかし、「そうやって生き延びているなら、よかったね」というわけにはいかない。絶妙なバランスの上で成り立っている生態系が変わることで、不具合も生じている。
ミスマッチで崩れる生態系
たとえば、「死のユリ」とも呼ばれるリシリソウは、30年前と比べて2週間ほど開花が早まっている。しかし、リシリソウの蜜を吸い花粉を集めるヒメハナバチが冬眠から覚めるタイミングは30年前と変わっていない。そのためヒメハナバチは食料を得られる期間が短くなり、子孫を増やすことができなくなっている。また、リシリソウとしても唯一の送粉者の到来が遅れることになり、開花に費やした貴重なエネルギーが無駄になっている。温暖化はこのようなミスマッチを多数生み出しているのだ。
北米に住むヒグマがサケを食べなくなったというのも驚きだった。冬眠を控えたヒグマはこれまで、遡上してくるサケをたらふく食べた後にエルダーベリーの実を食べていた。しかし、温暖化でベリーの実りが早まったことで、サケが遡上する時期とベリーが実をつける時期が重なってしまった。冬に向けて太りたいヒグマは、サケよりも確実に太れるベリーを選んだのだ。これで困ったのは、これまでヒグマが食べ残したサケの死骸を食べていた清掃動物たちだった。彼らの食料が減ったことは、森の生物多様性に大きな影響を与えかねない事態なのだという。
温暖化に対応できずに、絶滅の危機に瀕している生き物もたくさんいる。本書の冒頭に登場する砂漠の植物「ジョシュアツリー」は移動の手段を絶たれてしまった。1万年以上前までは 体長3メートルにも及ぶオオナマケモノにその実を食べさせることで生息域を広げ、生存に適した気候の中で生きていた 。しかしオオナマケモノが絶滅してしまったために移動の手段を奪われた今は、ただひたすら暑さに耐えるか、耐え切れずに生息域を減らしていくかの運命にある。
温暖化の影響はゲリラ豪雨や干ばつのような目に見える変化だけではない。私たちの目には見えにくいところで、多くの生き物たちがその生き方を変えている。本書が提示した多くの実例を読めば、生態系に起きている小さな変化が巡り巡って大きな絶滅につながる可能性があることを、かなり実感を持って学べるはずだ。人間は生き方を変え、真剣に温暖化対策に取り組まなければならない。本書はその助けになるはずだ。(鈴木裕也・科学読み物研究家)
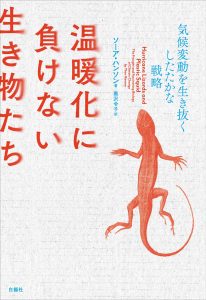
⇒noteで『温暖化に負けない生き物たち』のはじめにを試し読みいただけます
白揚社だよりVol.22
*クリックすると拡大して、お読みいただけます。ぜひ他のコンテンツもご覧ください。
表