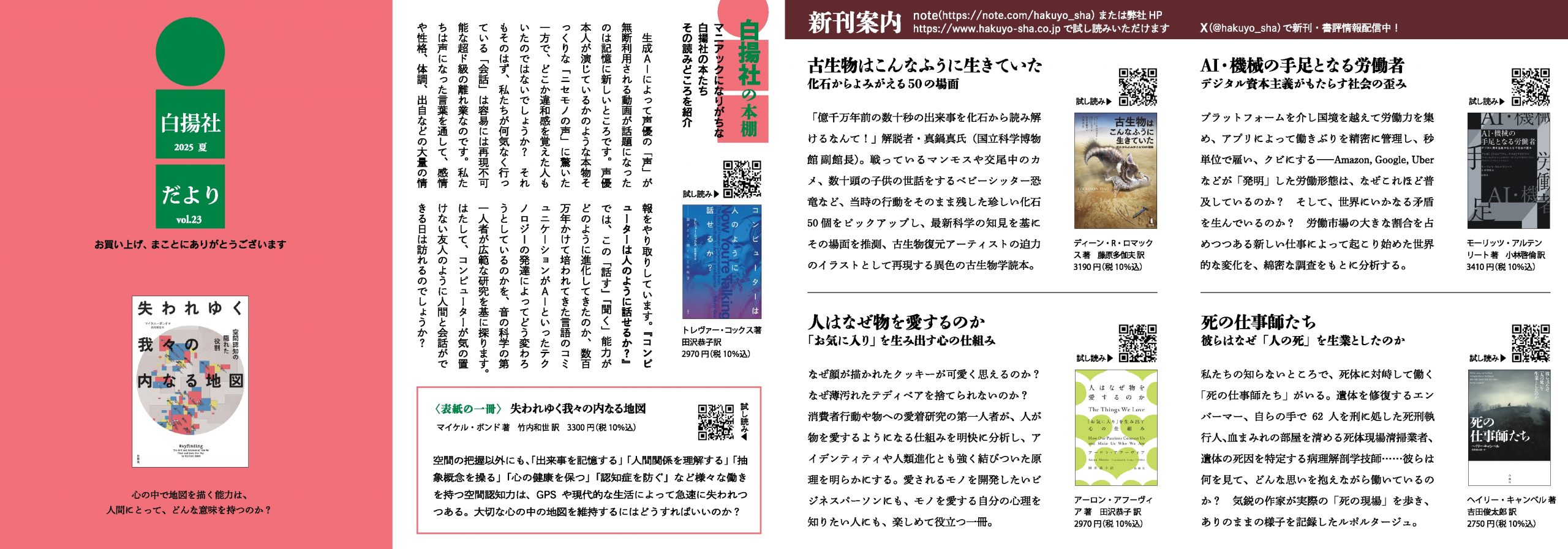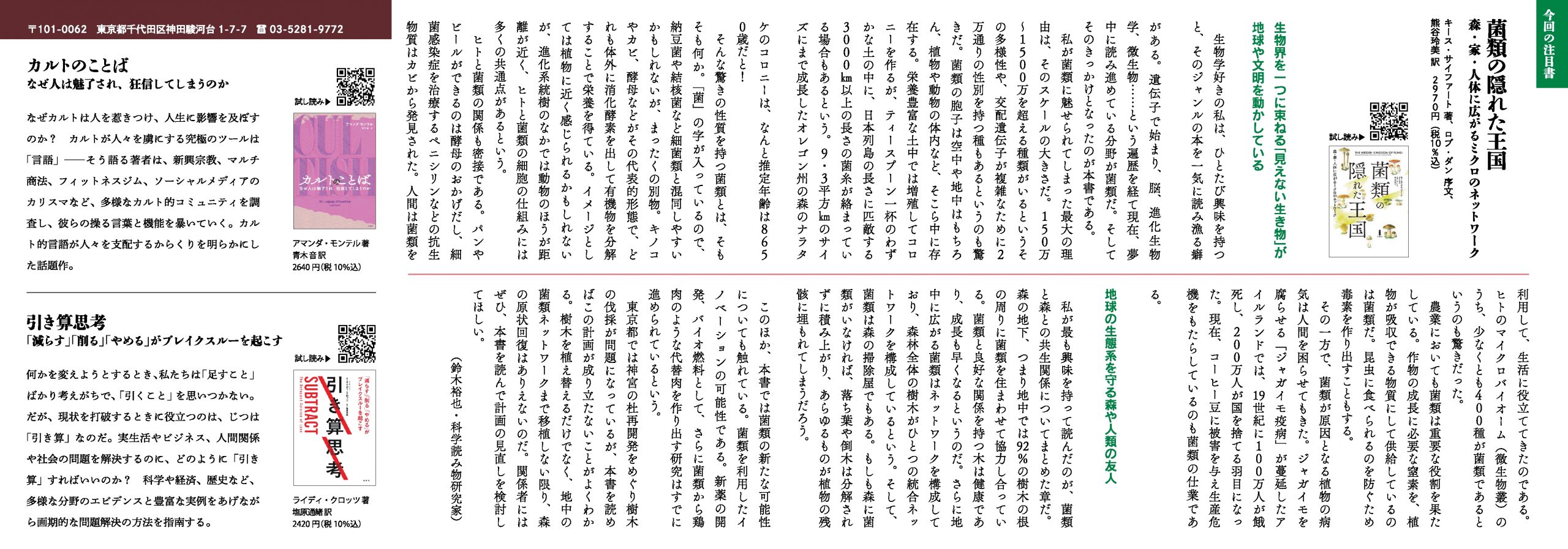科学読み物研究家・鈴木裕也の書評で読む『菌類の隠れた王国』
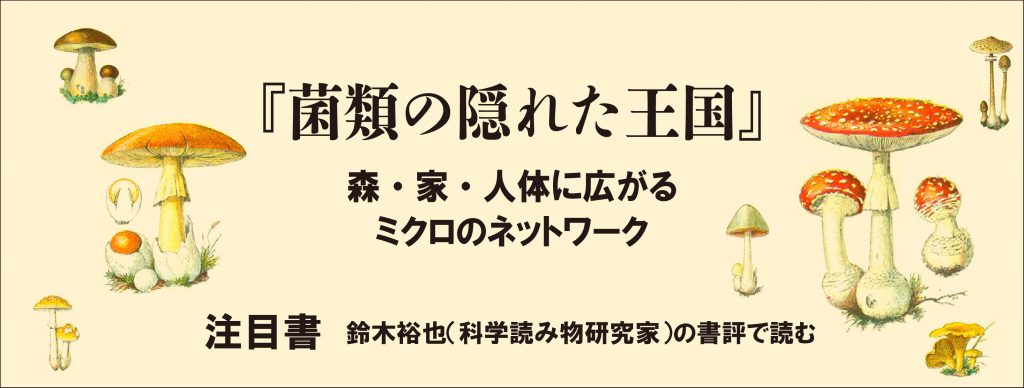
一般向けポピュラーサイエンス読み物を読み漁り、書評を書くライター・鈴木裕也さんが選んだ、イチオシの本を紹介するコーナーです
(白揚社の書籍に挟んでいる「白揚社だよりvol.23」からの転載)
◆
生物界を一つに束ねる「見えない生き物」が
地球や文明を動かしている
生物学好きの私は、ひとたび興味を持つと、そのジャンルの本を一気に読み漁る癖がある。遺伝子で始まり、脳、進化生物学、微生物……という遍歴を経て現在、夢中に読み進めている分野が菌類だ。そしてそのきっかけとなったのが本書である。
私が菌類に魅せられてしまった最大の理由は、そのスケールの大きさだ。150万〜1500万を超える種類がいるというその多様性や、交配遺伝子が複雑なために2万通りの性別を持つ種もあるというのも驚きだ。菌類の胞子は空中や地中はもちろん、植物や動物の体内など、そこら中に存在する。栄養豊富な土中では増殖してコロニーを作るが、ティースプーン一杯のわずかな土の中に、日本列島の長さに匹敵する3000㎞以上の長さの菌糸が絡まっている場合もあるという。9・3平方㎞のサイズにまで成長したオレゴン州の森のナラタケのコロニーは、なんと推定年齢は8650歳だと!
そんな驚きの性質を持つ菌類とは、そもそも何か。「菌」の字が入っているので、納豆菌や結核菌など細菌類と混同しやすいかもしれないが、まったくの別物。キノコやカビ、酵母などがその代表的形態で、どれも体外に消化酵素を出して有機物を分解することで栄養を得ている。イメージとしては植物に近く感じられるかもしれないが、進化系統樹のなかでは動物のほうが距離が近く、ヒトと菌類の細胞の仕組みには多くの共通点があるという。
ヒトと菌類の関係も密接である。パンやビールができるのは酵母のおかげだし、細菌感染症を治療するペニシリンなどの抗生物質はカビから発見された。人間は菌類を利用して、生活に役立ててきたのである。ヒトのマイクロバイオーム(微生物叢)のうち、少なくとも400種が菌類であるというのも驚きだった。
農業においても菌類は重要な役割を果たしている。作物の成長に必要な窒素を、植物が吸収できる物質にして供給しているのは菌類だ。昆虫に食べられるのを防ぐため毒素を作り出すこともする。
その一方で、菌類が原因となる植物の病気は人間を困らせてもきた。ジャガイモを腐らせる「ジャガイモ疫病」が蔓延したアイルランドでは、19世紀に100万人が餓死し、200万人が国を捨てる羽目になった。現在、コーヒー豆に被害を与え生産危機をもたらしているのも菌類の仕業である。
地球の生態系を守る森や人類の友人
私が最も興味を持って読んだのが、菌類と森との共生関係についてまとめた章だ。森の地下、つまり地中では92%の樹木の根の周りに菌類を住まわせて協力し合っている。菌類と良好な関係を持つ木は健康であり、成長も早くなるというのだ。さらに地中に広がる菌類はネットワークを構成しており、森林全体の樹木がひとつの統合ネットワークを構成しているという。そして、菌類は森の掃除屋でもある。もしも森に菌類がいなければ、落ち葉や倒木は分解されずに積み上がり、あらゆるものが植物の残骸に埋もれてしまうだろう。
このほか、本書では菌類の新たな可能性についても触れている。菌類を利用したイノベーションの可能性である。新薬の開発、バイオ燃料として、さらに菌類から鶏肉のような代替肉を作り出す研究はすでに進められているという。
東京都では神宮の杜再開発をめぐり樹木の伐採が問題になっているが、本書を読めばこの計画が成り立たないことがよくわかる。樹木を植え替えるだけでなく、地中の菌類ネットワークまで移植しない限り、森の原状回復はありえないのだ。関係者にはぜひ、本書を読んで計画の見直しを検討してほしい。
(鈴木裕也・科学読み物研究家)
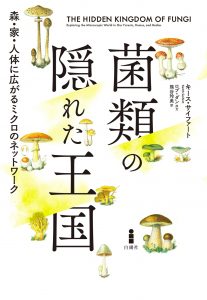
⇒noteで『菌類の隠れた王国』のイントロダクションを試し読みいただけます
白揚社だよりVol.23
*クリックすると拡大して、お読みいただけます。ぜひ他のコンテンツもご覧ください。
表